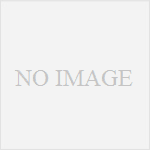人は誘惑に弱い生き物である。ぼくもすぐオフトゥンに吸い込まれるし、ポテトチップに手が伸びる。そんな自分を克服するために、「スタンフォードの自分を変える教室」(ケリー・マクゴニガル/大和書房)よんだ。
題名:スタンフォードの自分を変える教室
著者:ケリー・マクゴニガル
出版社:大和書房
ISBN:978-4-479-79363-2
発売日:2012/10/31
概要
意志力を強くする方法を、脳が人に及ぼす行動を調べた実験を用いて説明。衝動自体はなくならないが、衝動を抑制する機能は備わっている。大いなる目標を立てることで衝動を制御できる。なんでもフラフラと手をだす自分から抜け出したいひとへ。
感想
日々感じるストレス・欲求にどのように対処していけばよいのかがわかった気がする。また、自分がなりたいもの、成し遂げたいことを明確に決める必要があることを学んだ。
気になったポイント
意志力は前頭前皮質(目と額のうしろ)が大きく関わっている。前頭前皮質は大きく分けて3つの部分にわかれている。脳の右がやる力、左がやらない力、真ん中が望む力。望む力が一番強い。何にも負けない目標になる。
上記を踏まえたこの本のキーメッセージがこちら。
衝動自体はなくならないが、衝動を抑制する機能は備わっている。何にしたがって衝動を抑制するのか。それを決めるのは大いなる目標。
本書の原題も、「The Willpower instinct」。望む力をもつことで、いろんな欲求を制御できるようになる。けっして抑えるわけじゃない。制御できるようになる。
この観点に立ったうえで、日々の欲求にどのように打ち勝つのか、細かい対処法をいくつか取り上げる。
「なぜ」を考えれば姿勢がかわる。
よくやった!と自分をほめ、次は「わるいこと」をしてもいいと思ってないか?
例えば、勉強を30分したから、そのあと30分ゲームしよか、的な感じ。
いいこと、悪いこと、を判断基準にするのではなくて、すべて目標達成のためにどうだったか?で考える事。目標を達成するにはこれをやってていいんだっけ?そう考えると統制がききやすくなる。
そして、人間はホントに流されやすい。今日できたから明日も大丈夫、という感じで楽観視すると結構な確率で明日はやっぱりだらけてしまう。
明日も同じ行動をする!と思うこと。
一度負けてみる
何かしたい!と思ったら、快楽の誘惑に一度思い切って負けてみる。その際は、自分の期待がどれだけか見積もっておく。
ポテチ食べたい!と思っている自分に気づいて、どのくらい満足できるかな?と想像して、食べちゃう。
すると意外と思ってた以上に満足感はすくないもの。普段何も考えずに選んでいた行為の、実際の期待と満足感に気づくことができる。そうすれば次から自分で選んでコントロールできる。
欲求に対して真っ向から対抗すると、結局負けた!という感情でなんだか自分がどんどんダメ担っていく感があった。
そうじゃなく、いちど自分の欲求に気付き、それを認める、というステップを踏むだけで、自分でコントロールできるようになる、というのは非常に救われる気持ちがある。
あと、我慢できるならこちらもオススメ、とかいてあったのは何かやりたくなったら、10分待つ!ということ。
気持ちを抑えるのではなく、10分後にはしてもいいと思う。その間、なりたい自分をイメージするようにすれば、1つ目の「なぜ?を考える」というところにもつながって、我慢できるかもしれない。
自分を許す
何か失敗をしたときも同じ。だめだったことを考えているうちは、何を考えても「だめだ!」という解釈から入ってしまう。
そうではなく、一度自分を許す。自分を許すことで失敗から立ち直れる。恥や苦しみにさいなまれることなく、ありのままの事実を捉えられるようになる。罪悪感で失敗を繰り返すことを防ぐことができる。
自分を許す、というのはやっぱりムズカシイ。ぼくも過去のことを考えて暗い気持ちになることがある。それを受け止められるようになるのはいつかわからんけど、まずは許すことをトライしてみようと思う。
まとめ
ホントに、まず欲求に気づいて、それを制御する。制御するには目標を基準にする。これにつきる。
大きな目標を持つことで、日々の行動を律する事ができる。という話。これにはさらに、最終目標を描いた上で、短期・中期で達成すべき目標まで細分化していけば良いと思う。
ぼくで言うと最終の目標のないボンヤリした人間なので、それを探しつつ毎日行動するようにしたい。
ということで今日のほんあく
- やりたくなったら10分待って期待量を推し量る。
- 細かいところの目標を達成した自分像を持つ。
- 最終的になりたいもの・作りたいものを探しながら行動する。
ちなみにこれはフォトリーディングを使って読んだ。
全体を捉えた!という気分がある。非常によろしい。
これからもフォトリーディングばりばりでやっていこう。
ほなまたね。