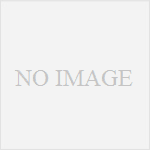ヒトの無意識には強い力があるらしい。フォトリーディングもその力を利用した本の読み方だった。それを理解するには脳のことをしっかり理解することが大事!ということで今回は「脳が冴える15の習慣」(築山 節/生活人新書)よんだ。
題名:脳が冴える15の習慣
著者:築山 節
出版社:生活人新書
ISBN:978-4-14-088202-3
発売日:2006/11/10
概要
ことあるごとに間違った対処をすると、脳は簡単に負のスパイラルにはいってしまう。そうならないよう脳の力を引き出すために、日々習慣として身につけておくべき15のことを紹介。日々の生活を少し向上させたいひとにおすすめ。
所感
日々、いろいろな選択をする。そのたびに楽な方に流されていると、一生そんな判断しかできなくなってしまう、そんなのはいやだ、と思った。自分が流されがちなところがあるので、それを改善せなあかんな。本の構成がわかりやすく、要点がつかみやすかった。
気になったポイント
この本では15の脳のためになる習慣を紹介していた。そのなかでも、今の自分にビビっときたポイントがあったのでまとめておく。
小さく自分を律する
脳を鍛えようと思った時、特に重要なのは前頭葉を鍛えること。前頭葉は、入力情報を記憶と組み合わせ、思考や行動を組み立てて司令を出す。
ここで、毎日自分を小さく律することが、大きな困難にも負けない耐性をつくる。
具体的には、「あ、これめんどくさいな」と思ったときに、それをめんどくさいからやらないではなく、実行に移していく。ぼくでいうと、食器洗いとか洗濯とかなんかな。こうすることで、前頭葉に司令を出させて、司令の力を大きくする。
これは昔パパイヤ鈴木がダイエット法で紹介してた、「2択ダイエット」と似てる。
なにか選択する場所に立った時に、腹が凹みそうなほうを選ぶというもの。例えばエスカレーターと階段どっち使って上いこ→階段やろ!てなぐあいに。
小さく律するというのは、それと同じことやろなあと。
そして「まじでめんどくさい!」というやつでも、その前の段階を細かく切っていくことで、自分が実行できるものに落とし込んでいくことが続けるコツなのかな、と思った。
自分が良くなりそうなほうを常に選択していきたい。
忙しい時ほど整理する
前頭葉は物事を選択・判断し、系列化して捉えている。パニックになっているときをイメージすると、ほしい情報がなんだったか、言いたいことはなんだったか、まったくごっちゃになっていることがあると思う。
これを系列化していくには、なにかきっかけを与えてやるのが大事。
そのためにも、まずは視覚的なところから。忙しい時ほど、身のまわりの整理をする。これは人が見てもわかるくらいにやっておくとよい。
整理された情報を脳に入力することで、自然と脳が情報を選択・判断して系列化してくれるようになる。
朝起きた時に机の上キレイやったらすっとするもんね。あとは一旦片付けに集中することで落ち着くこともできるかもしれない。
寝る前には、机の上を整理して明日やりたいことをなんとなく決めておいてから寝るようにしたい。
きっと明日の朝には脳がよい感じに情報を整えておいてくれるはず。
伝えることを前提にする
これはいままで見てきた、本の読み方と非常に似通ったところがあるが、人に伝えることを前提として情報を取得する。というもの。
伝えることを意識することで、要点を意識的に捉えられる。自然と脳にフィルターがかかる感じなんやと思う。
そしてこの捉え方を訓練していくことで、よりするどい情報にたどり着くフィルターが作られていくのかと。情報の捉え方として、やっぱりできる人は意識しているものなんやろな。
そして情報の掴み方として紹介されていた習慣は、情報はイメージでつかむ、というもの。
会議とかで議事録をばーっと取ってても、ただ書き取っているだけになって、あまり頭に入ってなかったことって結構ある。
そんなかんじでただ情報を受け取るのではなく、イメージ、つまり自分の解釈してとらえることで、あとから引き出しやすくなる。
また、イメージとして持っておくと、後でその情景を共有することを目的とすることで、他の人にも伝えやすくなる。
ここは自分が昔から意識していることなのですんなり理解できた感じがある。最近で言うと、ノートも絵で取るようにするようにしている。
そうすると、確認することも簡単になるし、なにより楽しく情報と向き合うことができているように思う。
まとめ
いくつか気になった習慣を書きだした。これらを意識しながら生活することで少しずつ日々の行動を改善していきたい。
ということで本よみからのアクション
- めんどくさい。と思ったら、やる。
- 机の上を整理して寝る。
- 聞いた話の確認の時に絵やジェスチャーを使う。
いい感じの本でした。
薄くて読みやすかったんでおすすめです。
しっかり実行していきましょう。
ほなまたね。